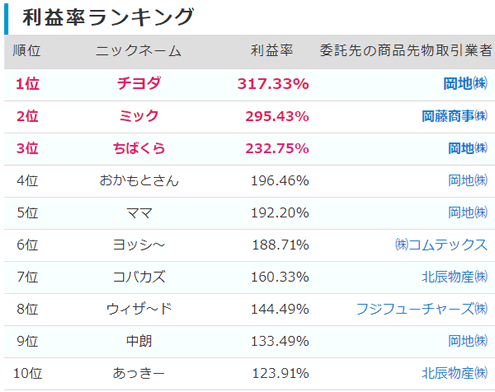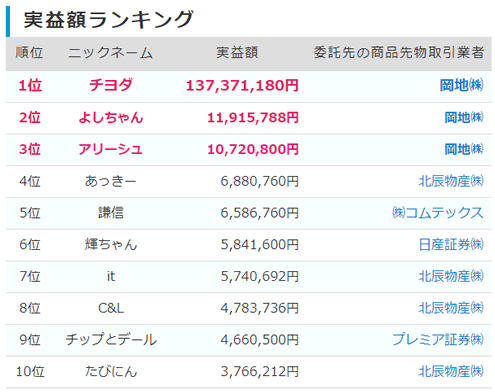今年は東北東
来る日曜日は節分だが、先々週あたりから各所で恵方巻の試食を勧められる事が多くなり、今年もまたこのシーズンが来たなと改めて感じる。恵方巻といえば近年はノルマや売れ残り余剰商品の大量廃棄等が社会問題になりつつあり、一部のスーパーで出した「もうやめにしよう」との意見チラシも話題になったのを思い出す。
さてその実態はというとミツカンの調査によれば恵方巻を食べる人の割合は直近では15年がピークで、昨年は61.1%と3年連続で前年を下回るなど微減傾向にあることが発表されている。やはり習慣として根付いているのか西日本が高い傾向にある模様だが、ちなみに私の周りでは豆撒きはやっても毎年恵方巻を食べる向きは皆無である。
こんな事もあってか今年は農林水産省が日本チェーンストア協会など流通業界に対し恵方巻の作り過ぎを控えるようにと異例の要請をするまでになったが、結局のところはスーパーやコンビニの商戦が過熱する一方でその需要が追い付いていないというところだろう。他に蒲焼等も問題になった事があるが食品ロス問題でナーバスになっている昨今、商材を特定して要請するような動きは今後まだ出て来る可能性は高いか。