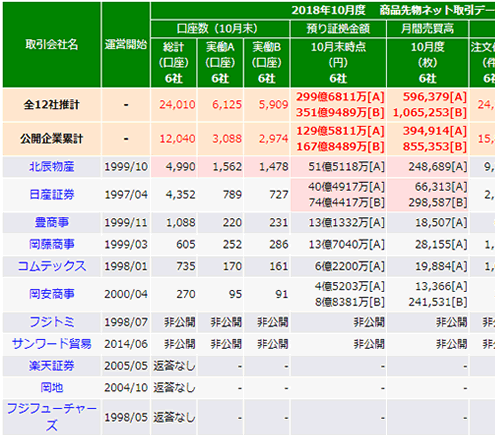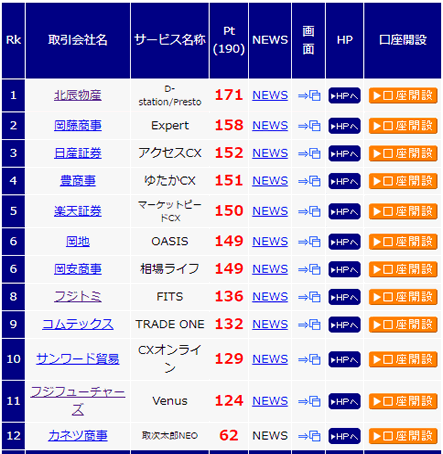自動取引増殖
さて、年明け早々に1ドル104円台まで瞬間急騰した円相場も週明け本日は1ドル108円台後半への円安ドル高が好感され日経平均は節目の20,500円を超えてきた。ところでこの為替といえば先週の日経紙総合面には「虚、突かれた個人投資家A・I」と題し、新年早々の外為市場でわずか1分の間に1米ドルに対して4円も急騰した背景には円安に安住した個人投資家が狙われ、それを見たAIのロスカットが拍車をかけたとの旨が書かれていた。
こうした相場の珍事?の素地としては一定のレンジが続くと見た向きがそれに即したストラテジーを組んでいるパターンが多く、酷かった例では東日本大震災時の225オプションのプレミアム狙いのセルボラ等が思い出されるが、今回の件も昨年10月から年末までの円相場が110〜114円と狭いレンジで動き金利狙いのホルダーが多かった事が円高に拍車をかけた格好になった。
また冒頭の通り近年は自動取引の存在感が高まり、為替に限らず株価変動も日米共に昨年12月は2008年のリーマン・ショック直前を上回るほどになっており世界規模で激しさを増している。自動取引の功罪については当欄でも何度も触れているが、リスク・パリティ型やテキストマイニングなどAIを活用するモノも増殖する日進月歩でこうした構造変化の是非論もまた議論対象になりそうである。