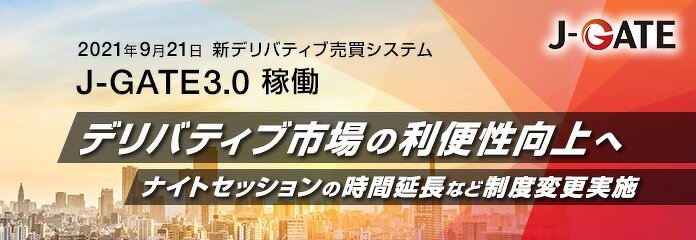コメのガラパゴス化
さて、今から10年前に試験上場が始まりこれまで2年ごとの期限延長を続けてきたコメの先物取引だが、先週末には大阪堂島商品取引所から本上場への移行が農林水産省に認可されなかったとの発表が為されている。試験上場として72年ぶりの復活であったが、4回にわたる延期も取引所として市場継続性を担保したいとの判断もあっただろうがこれ以上はメドもつかないと完全撤退を判断した格好か。
当欄でもこれまで約10年この経緯を追ってきたが、予てより上場企業大手の会員資格取得に続きSBIとも提携して売買システムの提供を受けいろいろ紆余曲折もあったものの、今年に入ってからはこのSBIHDが主要株主となり株式会社化を実現、取引量など各所では改善傾向にあったのも虚しく本上場申請の度に認可条件が変えられるなど守旧派の壁を崩すには至らずであった。
上記の通り認可基準も曖昧で生産者側も農水省の納得のゆく説明も無いと批判する声も多いが、言わずもがなJAグループや自民党の農林族には守旧反対派が幅を利かせており次期衆院選が近いなかJAなどへアピールを狙った動きとも取れなくもない。いずれにせよこれでまたコメ産業の競争力向上どころか、市場競争を避ける旧態依然の形態が継続される事となるか。