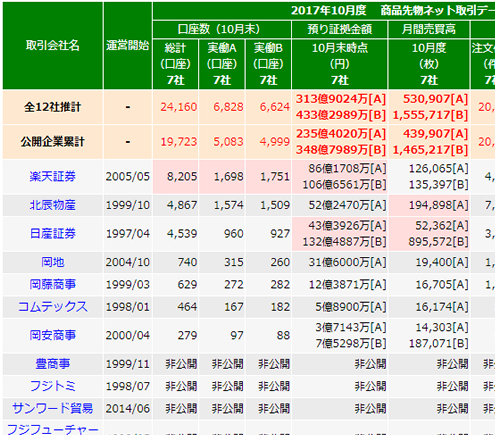ナイト需要
昨日の日経紙夕刊一面には「地下鉄24時間運航 月曜午前休みに」と題し、昨日までに自民党の時間市場創設推進議員連盟が地下鉄の24時間運航や月曜午前中を休みにする新制度導入など、夜間の観光振興につなげる提言をまとめた旨が載っていた。
しかしプレミアム・フライデーなど、七曜もヨコ文字にして冠にいろいろ飾りを付けると効果は別としてそれなりに何ぞや?とある程度の関心を惹くが、今度はココでは日本人旅行者が日曜日の夜に活動し易いよう月曜の午前を休みにするラグジュアリー・マンデーなる制度創設も盛り込むという。
また自治体で夜間観光の活性化を担う環境整備の旗振り役としてナイトメイヤー設置も併せて盛り込み国土交通省や警察庁に提言し実現を働き掛けるなど、5兆円の経済効果をあて込み2020年までの実現を目指すというが、一方ではカジノ問題よろしく治安悪化を懸念する声に労働時間から省エネまで課題は山積みで日本の夜の清き水もここから紆余曲折か。