第1回TOCOMリアルトレードコンテスト結果発表!1位は利益率296.37%!
東京商品取引所は、商品先物市場における取引の活性化、商品先物市場への参入促進等を目的として2017/6/19-8/31の期間で開催した「第1回 TOCOMリアルトレードコンテスト」の最終結果が9/14に発表されました!

▼第1回TOCOMリアルトレードコンテスト最終ランキング(2017/9/14発表)
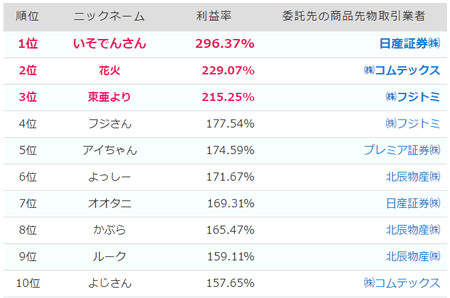
第一回TOCOMリアルトレードコンテスト最終ランキング
1位のいそでんさんはなんと利益率296.37%という結果に。
TOOCMリアルトレードコンテストの表彰式&入賞者トークセッションは、9/23に開催の「コモディティフェスティバル2017 in 東京」の会場にて行います。お楽しみに!
▼コモディティ投資をじっくり学べる一日「コモディティフェスティバル2017」
