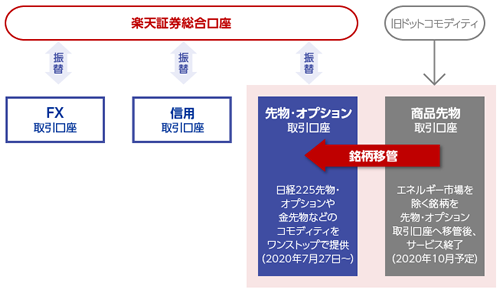2020年経営者よそう
さて年初といえばもう恒例の日経紙「経営者が占う」シリーズだが、今年もまた当欄で振り返ってみたい。日経平均の高値予想は平均で23,925円であったが12月の高値24,091円に対してほぼ的中水準、また安値予想の方も平均で19,110円であったがこちらも1月の安値19,241円に対してほぼ的中であった。
ところで当れば凄かったが、長年のあいだ万年強気とほぼ願望で固める暗黙ルールの中で年初安の年末高と判で押した予想しかしない大手証券社長と違って、ネット系では大手カブドットコム社長など昨年年明けのWBSで年平均は17,500円台と予想、右肩下がりの展開で「もう2万円はないと思う」と大胆に予想していたが結果的に大外れしてしまったもののこうした意見が出てきたのは面白い。
結果的に年末高で個別の有望銘柄として選ばれたモノも1位のトヨタ自動車、2位の信越化学から3位のソニー以下まあどんな銘柄を選んでいたとしてもいずれも素晴らしいパフォーマンスであったが、今年もこの有望銘柄のベストスリーは変らずその順番が入れ替わっただけとこの辺は手堅く置きに行ったという感じ。
というワケで今年の日経平均の高値予想は平均で25,450円となっていたが、毎回えいやっという感じで高値は12月の27,000円などと大風呂敷を広げる某大手証券社長などはさて置き、総じて6月に高値を付ける見方が多い。一方で安値予想は平均で21,625円となっていたが果たして大納会にはどのような展開になっているか昨年同様に今年の「子繁盛」の相場に注目したい。