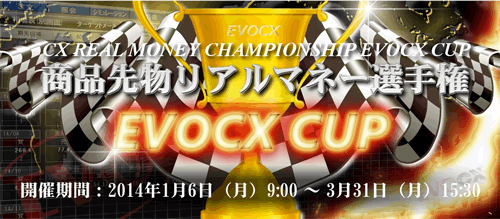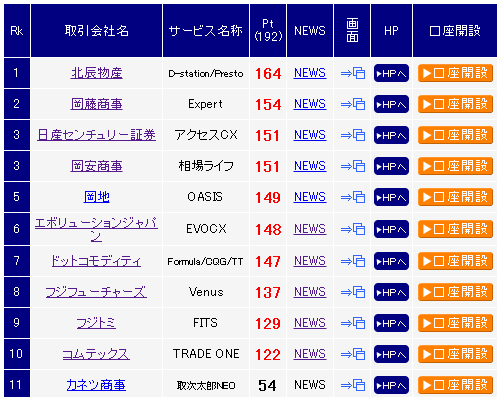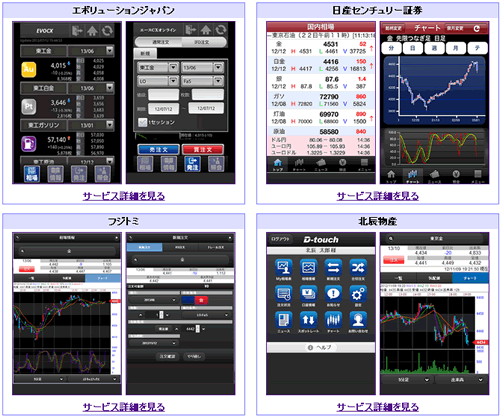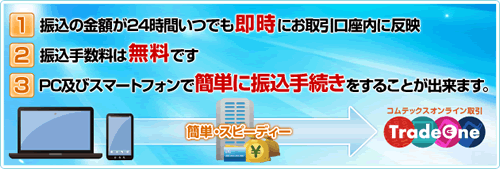1/6よりリアルマネー選手権「EVOCX CUP」開催
EVOLUTION JAPAN(旧エース交易)は、2014年1月6日(月)から2014年3月31日(月)15時30分まで、商品先物リアルマネー選手権「EVOCX CXP」を開催。
▼商品先物リアルマネー選手権「EVOCX CXP」
●主催
EVOLUTION JAPAN株式会社
協賛:東京商品取引所、コモディティTV
●開催日時
2014年1月6日(月) 9:00 〜 3月31日(月) 15:30
●対象者
EVOCXに口座をお持ちのお客様全員
<口座開設お申込み先>
http://www.evojapan.com/evocx/flow/index.html
●内容
1)OVER300コース(お預かり金額300万円以上)2)UNDER300コース(お預かり金額300万円未満)の2つに分かれて、開催期間中の収益率をお客様毎に計算し、ランキングを発表。各コース別で見事、上位1〜3位にランクインしたお客様には順位に応じてギフト券をプレゼント致します。
また、各コース上位3位までに入賞されなかったお客様にも、TOCOM賞、ビギナーズ賞、COMMDITY ONLINE TV賞をご用意いたしております。なお各プレゼント賞品の内容につきましてはCOMMDITY ONLINE TV内で発表いたします。
*ランキングは個人が特定できない形で発表いたします。
●賞品
【OVER300コース(お預かり金額300万円以上)】
1位・・・ギフト券10万円分相当、2位・・・ギフト券5万円分相当、3位・・・ギフト券3万円分相当
また、上位3名の方にはクリスタルトロフィーも進呈いたします。
【UNDER300コース(お預かり金額300万円未満)】
1位・・・ギフト券5万円分相当、2位・・・ギフト券3万円分相当、3位・・・ギフト券2万円分相当
また、上位3名の方にはクリスタルトロフィーも進呈いたします。
【特別賞】
1)TOCOM(東京商品取引所)賞
2)コモディティTV賞
3)ビギナーズ賞
『商品先物取引入門』(書籍)をプレゼント。対象者は2013年12月から2014年3月末までに口座開設申込いただき、リアルマネー選手権開催期間中(2014年1月6日 9:00 〜 3月31日 15:30)に、初回入金+取引(銘柄・取引枚数の条件は有りません)を行っていただいたお客様にもれなく、プレゼントいたします。
●対象銘柄
全取扱銘柄 (ミニ取引も対象)