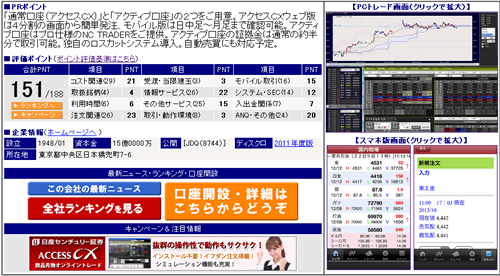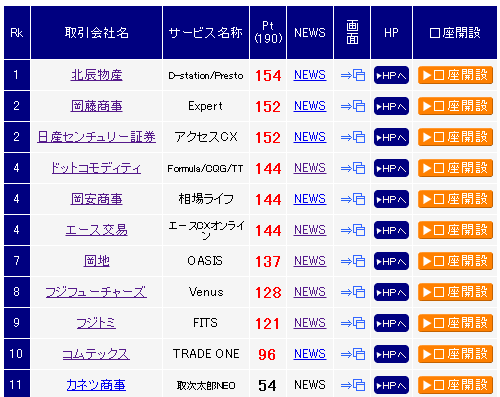週明けの本日も引き続き円安や政権交代期待を囃して日経平均は続伸となり、主力中心に個別も堅調相場となっていた。「家電御三家」も全般の雰囲気に呑まれ恐る恐る戻りに入っているが、直近ではパナソニックが1975年以来、実に37年ぶりの400円大台割れとなり、シャープは既に40年以上前の安値を更新、またソニーも1980円以来の32年ぶり安値に沈むなど最近では年足がしばしば活躍する始末となっている。
ここまでボロボロに売られた背景はパナソニックやシャープなど予想をはるかに超える巨額の赤字がサプライズであったが、黒を確保したソニーの場合、突如として15%超えの希薄化を生むCB発行の報がサプライズとなった模様で安心買いが付いた分余計にそのその投げ物も大きいものとなった。
ところでソニーといえば、社債でもCBならぬ株式連動社債が今年の夏場に外資系の発行体から売られたのが思い出される。その頃の株価は1,000円の大台を割ったり戻したりを繰り返しているような水準であったが、このノックイン判定水準が当初価格の60%の設定となっており約600円というところ、この手は販促のパンフ等の錯覚?効果もありノックインまで可也遠いという感覚に陥り易いがその後上記の通りの急落で一気に値位置が変わる等その行方は一気に不透明漂うモノに。
このノックイン債、幸いにも3桁の値頃感がある程度働いたことで105%で設定していた早期償還判定水準に抵触し第一回目で難無き?早期償還となったワケだが、昨今市場を取り巻く環境を鑑みるに株価にとっては寝耳に水のサプライズは何処に潜んでいるか分からず、この手の商品には十分な注意が必要なのはいうまでもない。