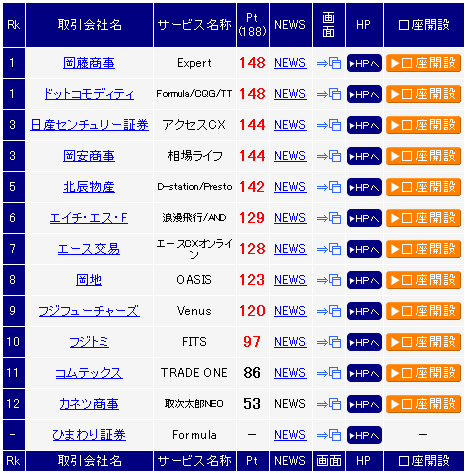本日より明日まで恒例の日銀金融政策決定会合があるが、日銀といえば先週此処の株が遂に40,000円の大台を下回ったのが話題になっていた。昨今の個別銘柄は実に20年ぶりとか30年ぶりの安値に沈む個別銘柄が多いが、当欄でこの日銀株に触れたのが8月でその時は約10年ぶりの安値であったが、これで実に約26年ぶりの安値になった。
さて株価の衰退よろしく段々と細ってきたのが、例の金融緩和策の一環として株価の下落局面で基金を通じ行うETF買いか。上記の8月は1日あたり256億円を買った日もありその買い入れ合計は1,732億円であったが、9月は同合計が1,561億円、そして10月は同合計が742億円、今月というと今のところは同合計が328億円と明らかに勢いが鈍っている。現在までに基金のETF購入総枠半分超を費やしたが、為替介入は一発で8兆円投入というからこの辺の采配は如何に。
しかし見ていると日銀総裁というのも影が薄い。バーナンキ氏など見ていると賛否両論あるものの一応は雇用拡大と経済成長を最優先課題に掲げる旨の明確化が目立つが、今の日銀総裁にはこうした責務の発言も無ければ明確なビジョンも全くといっていいほどない。先週末の日経紙「まちかど」ではこの日銀株が換金される様を「日銀株より日銀券を志向する投資家は、デフレがまだ続くと判断しているのかもしれない。」と書いてあったが、となれば介入効果も虚しくまだ円高継続という見方にもなるが。