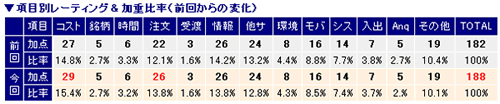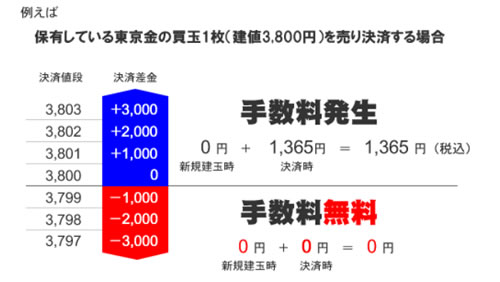曖昧加減とスケープゴート
さて、かつては山本モナさんと不倫騒ぎで有名になった原発担当相は今更ながら東電原発のメルトダウン確認で事実認定甘かったなどと認めていたが、この東電といえば先週末に政府が枠組みを決めた賠償スキームでは、新機構が東電に資金支援を行うことで破綻させないかわりに賠償総額の上限は設定せずに賠償は東電が負う事になった。
途中段階とはいえ一連の動きには大きすぎる公益企業の扱いの難しさが垣間見られる。今のところ株主責任は免れた格好だが、4/21付けの当欄では、「日本社会の構造は官民揃って責任の所在が曖昧になりがち」と書いた事がある。モラルハザードや詳細はまた後述したいがこのままゆくとそれこそ責任所在が曖昧なままなし崩し的な税金投入の穴埋めが膨らむ恐れがある。
また政府介入といえば直近でも中部電力があった。浜岡を止める話は全国の原発で30年以内に震度6強以上の地震が起きる確率が浜岡原発で84%と突出しているからとの事だが、福島第一原発は日経紙などにも載っていたが0.0%にもかかわらず今回の大惨事となったワケで、こう考えるとなにやらスケープゴートのようにも思える。事実、浜岡は原発依存度が比較的低く止め易いワケで、誰が絵を描いたのやらパフォーマンスに利用されただけか。
しかし法的な根拠が曖昧なままで政治が介入するのなら、電力だけでなく放送・通信など規制業種全般もいろいろな側面で再考する必要が出て来るし、もう一つ今後気になるのは外国人投資家のスタンス。こうも市場ルールを逸脱した発言が度々繰り返すのを彼らがどう解釈するかだが、周知の通り売買での大きなウエートを占めるだけにこの辺は注意しておかねばならないだろう。