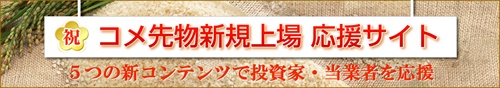サブの台頭
さて今年に入ってからは2月に触れたPTS取引だが、先月の主力7社(カブッドットコム証券、インスティネット証券、マネックス証券、SBIジャパンネクスト証券、松井証券、大和証券、チャイエックス・ジャパン証券)合計の月間売買代金が初の1兆円超となった旨が過日報道されている。
これをヒストリカルで見ると、10年2月の1,450億9700万円を底に順調に拡大、11年1月には5,000億円を超え、3月には9,800億円台にまで急増した。4月は前月比で減少となったものの、5月は再度増加。先にも触れたが、シェアが2%を超えると市場として無視できないという投資家が多く、利用に一段と弾みがつく可能性も出ている。
売買代金の増加傾向については一部外資が指摘するように、昨年10月に空売りが出来るようになり高速売買をする海外投資家が注文を増やしているという事や、国内ネット系では呼値が取引所売買よりも細かく設定されていることが顧客に浸透してきている事、一部では注文方法の多様化により取引所やPTS市場など複数市場の価格や成立し易さなどを判別し、最良と判断される市場へ自動で注文執行を行うシステムが稼動している事も大きな要因となっているようだ。
最近ではスマホアプリなど情報面の充実も後押しとなっており、欧米で見られたようにPTSの台頭が取引所再編を促進したような動きが日本で起きるか注目される。